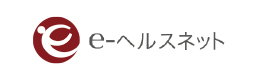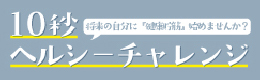出産に関係すること
- トップ
- こんなときどうする?
- 出産に関係すること
- 家族出産育児一時金 (出産したとき)
家族出産育児一時金 (出産したとき)
手続内容
被扶養者である家族が出産したとき、その出産費用の一部として家族出産育児一時金が支給されます。健康保険でいう出産とは、妊娠4 か月以上(妊娠85日以上)の出産をいい、生産、死産、流産、早産のいずれの場合においても家族出産育児一時金が給付されます。
給付は一 児ごとに給付され、双生児を出産された場合には二児分の出産育児一時金が給付されます。
家族出産育児一時金の支払いは、健保組合から分娩機関に直接支払うか(「直接支払制度」または「受取代理制度」)、被保険者が全額給付を受けるかを選択できます。直接支払制度または受取代理制度を利用した場合、出産費用が出産育児一時金支給額未満のときには、その差額を被保険者の請求により給付されます。
分娩機関と支給額
1児につき
50万円
産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合

|
1児につき |
産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合 |
|
1児につき |
産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合 |
※令和5年3月31日以前に産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は1児につき42万円
令和4年1月1日から令和5年3月31日に産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合は1児につき40.8万円
令和3年12月31日以前に産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合は1児につき40.4万円
但し、提出期限(出産の翌日から2年)を経過した申請を除く
手続時期及び届書様式・添付書類
1.直接支払制度
分娩前に健保組合への手続きはありません。
出産育児一時金の請求と受取を被保険者(被扶養者)に代わって、医療機関が行う制度です。
分娩費請求額が50万円(産科医療補償制度加算対象出産でない場合は48.8万円)未満の場合は、健保組合へ差額請求の手続きをして下さい。
※令和5年3月31日以前の出産については、分娩費請求額が以下の金額未満の場合に健保組合へ差額請求の手続きをして下さい。
・令和5年3月31日以前に産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は1児につき42万円
・令和4年1月1日から令和5年3月31日に産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合は1児につき40.8万円
・令和3年12月31日以前に産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合は1児につき40.4万円
但し、提出期限(出産の翌日から2年)を経過した申請を除く

2.受取代理制度
分娩前(出産予定日まで2か月以内であること)に健保組合へ手続きが必要です。
被保険者(被扶養者)が出産する医療機関等へ出産育児一時金の受取を委任し、当健保組合へ事前に申請することにより、医療機関等へ直接支給されます。
対象医療機関は、直接支払制度を利用できない医療機関のうち、年間の平均分娩取扱い件数が100件以下の診療所及び助産所や、正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所・助産所を目安として、厚生労働省に届出を行った分娩施設です。
提出期限
出産予定日まで2か月以内

3.健保組合に直接請求
直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを望まない場合、出産後に当健保組合へ直接請求し、支給を受けることができます。
この場合は、一旦全額を医療機関等に支払います。
提出期限
出産日の翌日から2年