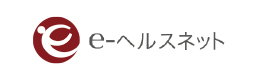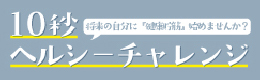限度額適用認定証
- トップ
- こんなときどうする?
- 限度額適用認定証
限度額適用認定証
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、 限度額適用認定証情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
手続内容
(1)マイナ保険証をお持ちでないなどの理由で「限度額適用認定証」の交付が必要な方は、事前に健保組合へご申請ください。
(2)高額療養費の自己負担限度額は被保険者の所得区分によって下表のとおりに分類されます。
※市町村民税非課税等の低所得者の方は健保組合への申請が必要です。「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで下表の自己負担限度額となります。
【 70歳未満 】
(ア)標準報酬月額830,000円以上
自己負担限度額:252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数該当:140,100円】

|
(ア)標準報酬月額830,000円以上 |
自己負担限度額:252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
(イ)標準報酬月額530,000円~790,000円 |
自己負担限度額:167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|
(ウ)標準報酬月額280,000円~500,000円 |
自己負担限度額:80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|
(エ)標準報酬月額260,000円以下 |
自己負担限度額:57,600円 |
|
(オ)低所得者(市長民税の非課税者等) |
自己負担限度額:35,400円 |
【 70歳以上 】
標準報酬月額530,000円~790,000円
現役並み所得者Ⅱ
自己負担限度額:167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数該当:93,000円】

|
標準報酬月額530,000円~790,000円 |
自己負担限度額:167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|
標準報酬月額280,000円~500,000円 |
自己負担限度額:80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
※被保険者が低所得者とは被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。ただし、被保険者が市区町民税が非課税等であっても、上位所得者に該当する場合の所得区分は上位所得者となります。
※療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた場合には、4か月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
(3)限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から1年間となります。申請書受付月より前の月の限度額認定証の交付はできませんので、日程に余裕をもってご提出ください。
手続きの流れ
①認定証の申請
「限度額適用認定証交付申請書」 に必要事項を記入し健保組合へ提出
「限度額適用認定証交付申請書」
②認定証の交付
健保組合から「限度額適用認定証」を交付
③認定証の提示・自己負担限度額の支払い
病院へ資格確認書と「限度額適用認定証」を提示し、高額療養費の自己負担限度額を支払う。
※保険診療外の医療費、食事負担額、差額ベット代等は対象外です。
手続時期及び届書様式・添付書類
被保険者が健保組合へ提出します。
提出期限
必要な時

返納について
次に該当した時は速やかに認定証を健保組合まで返納してください。
(1)被保険者が資格を喪失したとき
(2)対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき
(3)被保険者の所得区分が変更になったとき…標準報酬月額の改定により所得区分が変更になった方には、健保組合からご連絡します。再交付を受けるときは、「限度額適用認定証交付申請書」を提出してください。
(4)有効期限に達したとき…再交付を受けるときは、再度「限度額適用認定証交付申請書」を提出してください。
(5)70歳未満の対象者が70歳に達する月の翌月に至ったとき
(6)対象者が後期高齢者の対象者となったとき